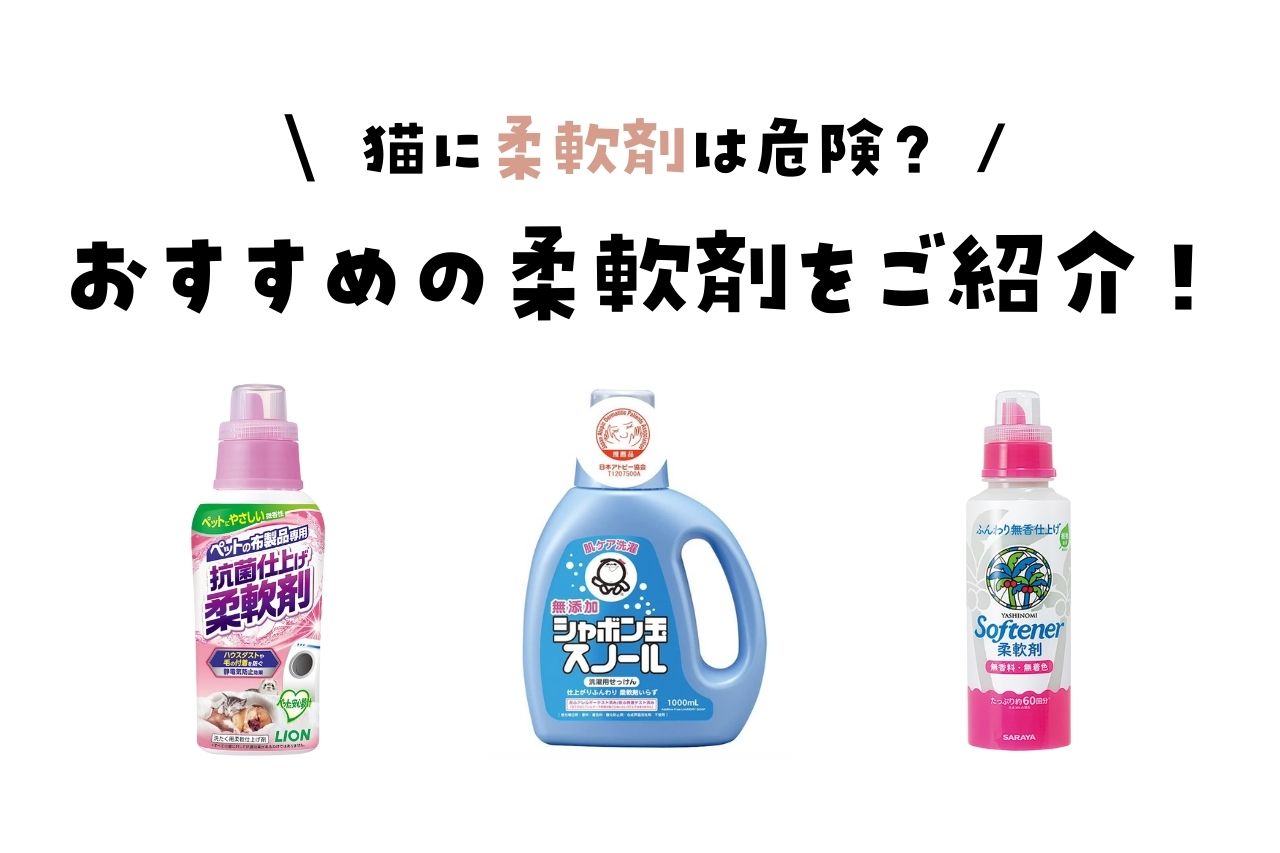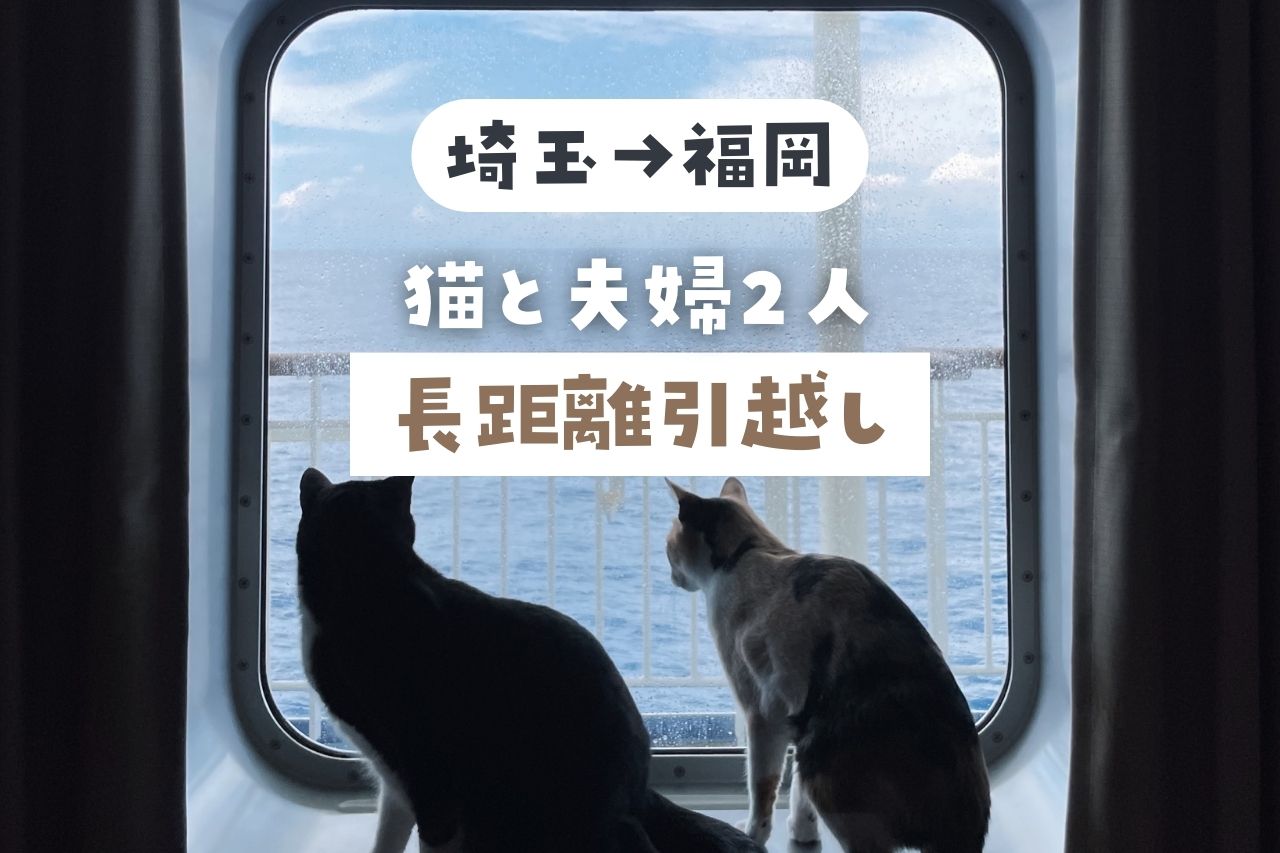飼い主
爪研ぎがあるのに壁をバリバリする・・・
飼い猫がソファーや壁紙に爪を研いでしまい、家をボロボロにしてしまう…と、お困りの飼い主さんは多いのではないでしょうか?
飼い主さんにとって猫の爪研ぎはかなり深刻な問題ですよね。
そこで今回は、猫が爪研ぎをする理由やしつけ方、爪研ぎにおすすめのアイテムについて詳しく解説します。
ソファや壁紙など、場所別の爪研ぎ防止策についてもご紹介するので、爪研ぎにお困りの飼い主さんはぜひ参考にしてみてくださいね!
猫が爪を研ぐ理由

猫が爪研ぎをする理由は、主に以下の5つです。
まずは、猫が爪研ぎをする理由を把握することが大切です。
以下で詳しく解説するので、対策やしつけをする際の参考にしてみてくださいね!
獲物を捕まえるため
肉食動物の猫にとって、爪は獲物を狩ったり自分の身を守ったりするために必要な武器です。
いざというときにすぐに使えるように、常に鋭い状態で保っておく必要があります。
猫の爪はバームクーヘンのような層になっているため、爪研ぎをすることで外側の古い爪が剥がれ落ち、新しい爪で常に鋭い状態をキープすることができるのです。

みけぽん
後ろ足は噛んで爪を剥がすにゃ!
縄張りや強さをアピールするため
猫の顔や肉球には臭腺と呼ばれる器官があります。
猫が壁や家具、飼い主さんなどにスリスリするのは臭腺から出た自分のニオイを擦り付けることで自分の縄張りや所有物を主張するための行動です。
また、自分の強さをアピールするときも爪研ぎをする習性があります。
猫が背伸びをしながら爪研ぎするときは、少しでも高いところに匂いをマーキングすることで、強さを主張したり自分を大きく見せたりするための行動だと言われています。
飼い主さんに構ってほしい
飼い主さんの目の前でわざと爪研ぎする場合は、飼い主さんへの構ってアピールの可能性が高いです。
過去に爪研ぎをしたことで、飼い主さんがやめさせるためにおもちゃで遊んであげたり、おやつを与えたりした経験はないでしょうか?
「これをしたらいいことがある!」と学習し、飼い主さんに構ってもらう目的で爪研ぎをする猫もいます。

ひげちゃん
爪研ぎするとおもちゃで遊んでもらえるにゃ!
気分を落ち着かせるため
ジャンプに失敗したり、どこかに身体をぶつけたりしたときに、失敗を誤魔化すかのように爪研ぎをすることがあります。
この行動は「転移行動」と呼ばれるもので、本来とは関係のない行動をすることで自分の気分を落ち着かせていると言われています。

飼い主
人間で言う「仕事のストレスでショッピングする」みたいなことかな?

みけぽん
その通りにゃ!
ストレス解消
来客などでストレスを感じたときやイライラしたときにも爪を研ぐことがあります。
ストレスを感じる理由は猫によってそれぞれですが、爪研ぎをすることで自分を落ち着かせようとしているのです。

ひげちゃん
僕もお客さんが帰ったあとに爪研ぎするにゃ!
爪研ぎをやめさせることはできない

猫の爪研ぎは本能なのでやめさせることはできません。
飼い主さんがどんなに叱っても、爪研ぎを止めることはないでしょう。
猫と暮らすためには猫の本能に寄り添い、快適に爪研ぎできる環境を整えてあげることが大切です。
猫はとても賢い動物ですが、叱っても理解できないことがほとんどです。
それどころか、壁やソファーで爪研ぎした猫に飼い主さんが叱ることで「構ってくれた!」と認識してしまい繰り返すようになることも。
また、体罰や大きな声で叱ってしまうと飼い主さんを「嫌なことをする人」と認識して怖がるようになることもあります。
せっかく築いた関係性を壊さないためにも、大きな声で叱ったり体罰でしつけたりするのは絶対にやめましょう。
猫の爪研ぎはしつけで治る!

猫の爪研ぎは本能的な習性なので、何もしなければあらゆる場所で爪を研いでしまいます。
猫を飼うなら何かしらの対策は欠かせません。
以下で、具体的な爪研ぎのしつけ方法についてみていきましょう。
子猫の頃からしつけることが大切
子猫は母猫など、ほかの猫の行動や仕草をマネするののが得意な動物。
人間と一緒に生活している猫にとっては、飼い主さんが母猫やほかの猫の代わりです。
そのため、子猫に爪研ぎを教えるときは飼い主さんが爪研ぎで爪を引っ掻く様子を見せてあげるのが最も効果的な方法と言えます。
飼い主さんが爪研ぎのお手本を見せたあとに子猫を爪研ぎの上に乗せ、肉球を擦り付けるように動かしてあげましょう。
最初はうまくいかないかもしれませんが、根気よく教えてあげることが大切です。
お気に入りの爪研ぎを見つけてあげる
「新しい爪研ぎを用意したのに全く興味を持ってくれない…」
「爪研ぎがあるのに壁やソファーで研いでしまう」
といったケースの場合は、自宅にある爪研ぎを気に入っていない可能性が高いです。
爪研ぎにはダンボールや麻などさまざまな素材のものがあり、猫によって好みが異なります。
最初のうちは素材や大きさ、形が異なる爪研ぎを複数用意してあげるとよいでしょう。
定期的な爪切りで被害を減らす
怪我の防止のためにも、猫の爪は定期的に切るようにしましょう。
爪を切ってあげることで、万が一してほしくない場所で爪を研いでしまっても被害を軽減することができます。
猫の爪切りの目安は下記の通りです。
- 子猫・・・10日に1回
- 成猫・・・2〜3週間に1回
ただし、猫の爪の伸び方には個体差があるので、愛猫の様子を見ながらベストなタイミングを見つけてみてくださいね!
爪研ぎの選び方

爪研ぎの素材は、主に「ダンボール製」「麻製」「木製」の3種類です。
猫によって好みはさまざまなので、愛猫に合う素材のアイテムを見つけましょう。
【ダンボール製】コスパを重視したい方におすすめ

ダンボール製の爪研ぎは1,000円以内のリーズナブルな価格のものが多いです。
ホームセンターやペットショップなどで手軽に購入でき、初めて爪研ぎを使う猫のお試し用にも向いています。
両面使える板型やおしゃれなデザインのソファー型など種類も豊富です。
メリット
- 形状やサイズ、デザインなどの種類が豊富
- リーズナブル
デメリット
- カスが出やすく散らばりやすい
- 寿命が短い
【麻製】爪研ぎのカスが気になる方におすすめ

ダンボールのカスが気になる方は麻製の爪研ぎがおすすめです。
素材がしっかりしているので力強く爪を研ぐ猫に向いています。
縦型でポール状のものが多く、壁などに立ち上がって爪を研ぐのが好きな猫や若くてヤンチャな猫に好まれやすいです。
メリット
- 買い換える頻度が少ない
- カスが落ちにくく掃除の手間が省ける
デメリット
- ニオイが苦手な猫もいる
- 高価なものが多い

飼い主
気に入ってくれるか不安な方は、1,000程度の安価なものから試してみてね!
【木製】柱で爪を研ぐ猫におすすめ

家の柱や木製の家具などで爪研ぎする猫には、木製の爪研ぎがおすすめです。
とくに、外で暮らしていた経験がある猫は、木で爪を研いでいた可能性が高く研ぎ心地が似ている木製を好む傾向にあります。
ダンボール製や麻製に比べて耐久性が高いため、ひとつのアイテムを長く愛用したい飼い主さんにもおすすめです。
メリット
- 耐久性が高く、買い替え頻度が少ない
- 壁に固定できるものが多く、省スペースで設置できる
デメリット
- 木クズが出やすくこまめな掃除が必要
- 3,000〜10,000円程度の高価なものが多い

飼い主
おもちゃと一体型のものなら、万が一気に入らなくても無駄にならないよ!
【場所別】猫の爪研ぎ防止策

最後に、壁やソファーなど場所別の爪研ぎ防止アイテムをいくつかご紹介します。
「どうしても壁で爪を研いでしまう…」とお悩みの飼い主さんは、ぜひチェックしてみてくださいね!
壁紙
壁紙で爪研ぎをするのが好きな猫には「爪研ぎ防止シート」がおすすめです。
爪が引っかからないようにツルツルとした素材になっており、壁に貼るだけ簡単に取り付けられます。
【 テカらずサラサラ!】キャットブリーダー監修 猫 壁紙保護シート


飼い主
我が家でも愛用しているアイテム!

みけぽん
きれいに剥がせるから賃貸物件にもおすすめにゃ!
柱
柱や壁紙のコーナー部分に爪研ぎする猫には、壁に取り付けるタイプの爪研ぎがおすすめです。
猫がいつも爪研ぎする場所の上から貼ってあげるとよいでしょう。
壁まもる君 コーナー用 壁紙タイプ

壁紙や柱の角に取り付けるタイプの爪研ぎです。
画鋲で止めるだけで取り付けられるので、設置跡が残りにくく賃貸住宅でも安心。


ひげちゃん
5種類の素材の中から猫の好みに合ったものを選べるにゃ!
ソファー
ソファーで爪研ぎをしてしまう猫には、ソファーに設置するタイプの爪研ぎがおすすめ。
ソファーを直接傷つける心配がないだけでなく、猫にとってはお気に入りの場所で継続して爪研ぎできるのがうれしいポイントです。
ソファー用 爪研ぎマット

こちらは、ソファーのコーナー部分に設置するタイプの爪研ぎ。
ゴム製の紐で簡単に取り付けられる手軽さもおすすめできるポイントです。
まとめ

今回は、猫の爪研ぎ対策についてご紹介しました。
我が家を猫の爪研ぎから守るためには、猫の気持ちを優先してあげることが大切です。
爪研ぎのしつけのポイントは下記の2つ。
- お気に入りの「爪研ぎ」を見つける
- お気に入りの「場所」を見つける
最近では、インテリアのデザインにマッチするおしゃれなアイテムも多く販売されています。
猫の好みを優先しつつ、飼い主さんにとっても快適に使える爪研ぎや対策グッズを見つけてみてくださいね!
こちらの記事もおすすめ!
– キャトヘルスアドバイザー
– 猫の健康管理インストラクター
– 保護猫歴10年
– 2匹の保護猫と暮らす
猫と飼い主さんにとって快適な暮らし、愛猫といつまでも楽しく暮らすための知識を得るサポートをします。