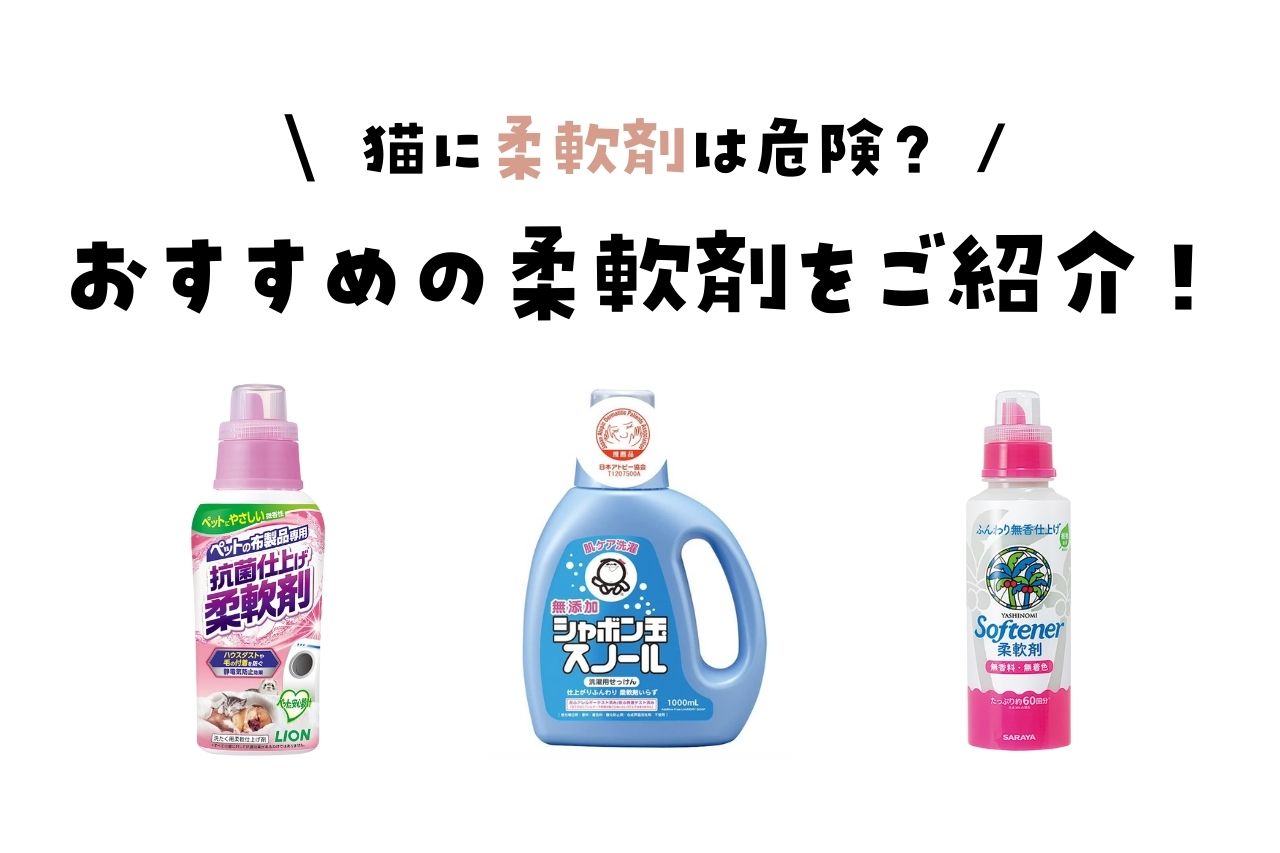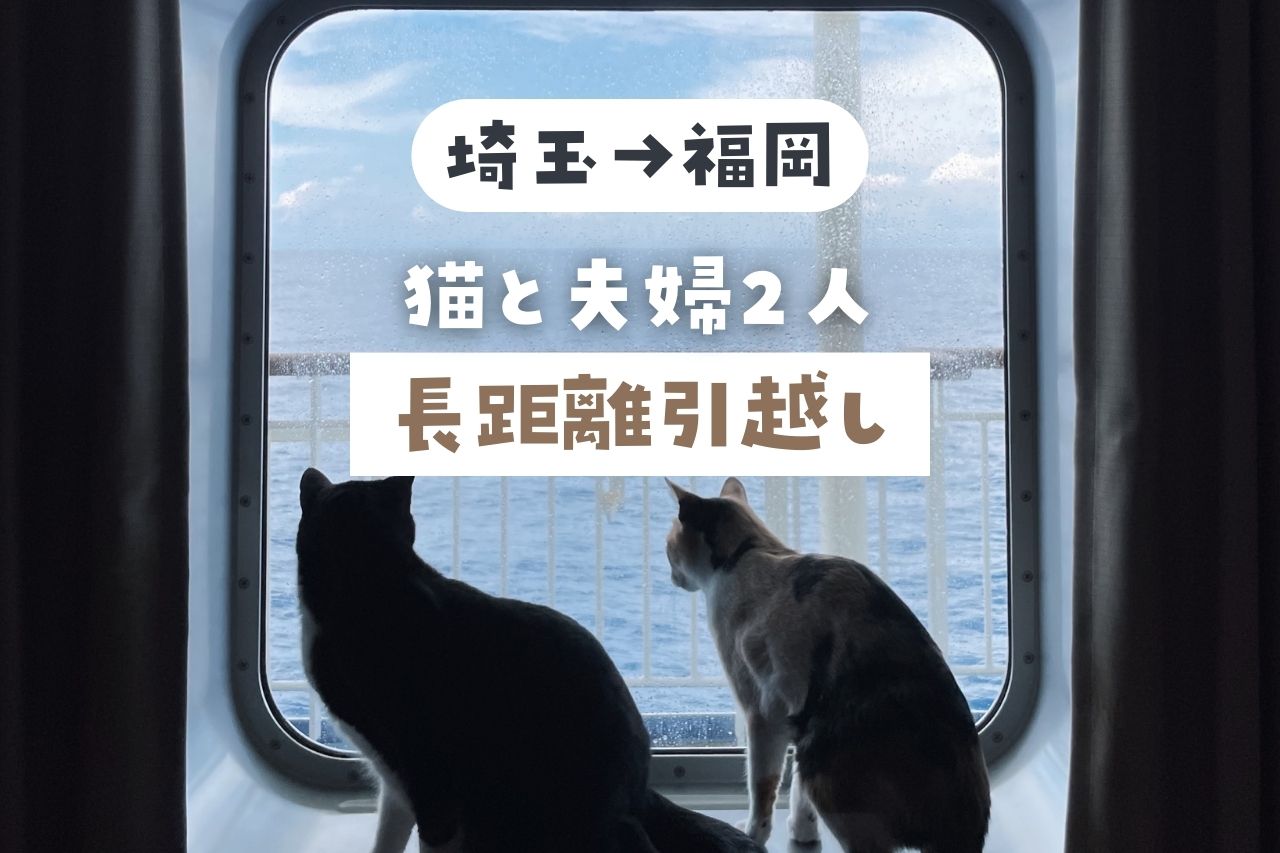愛猫との生活が落ち着いてきた頃「この子にも遊び相手が必要なのでは…」と、2匹目を考える飼い主さんも多いのではないでしょうか。
今回は、保護猫2匹と暮らす我が家が2匹目を迎えたときの実際の体験談を交えて、仲良くなるまでの期間や失敗しないために飼い主ができること、注意点などについてご紹介します。
これから2匹目を検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
新入り猫を迎える前にやるべきこと

新入り猫を迎える前に、まずは事前準備をしっかり行うことが大切です。
ここでは、新入り猫を迎える前にやるべきことをいくつかご紹介します。
先住猫の性格を把握する
まずは、先住猫の性格を確認しましょう。
猫も人間と同じように、猫との関わりが苦手な子や好き嫌いが激しい子、1匹を好む子など、それぞれの個性があります。
先住猫の性格が社交的なら新入り猫と仲良くなれる可能性は高いですが、神経質だったり猫が嫌いな子だったりすると多頭飼いが難しいことも。
先住猫と新入り猫の相性によっては、時間をかけても馴染めない場合もことを覚えておきましょう。
保護猫の場合は寄生虫や感染症などの検査
先住猫と新入り猫を同じ環境で飼育する前に、まずはお互いの健康状態や寄生虫、感染症の有無を検査しましょう。
とくに、保護猫の場合はノミやダニなどの寄生虫がついている場合が多く、ほかの猫との交流によって猫エイズや白血病などの病気にかかっていることもあります。
保護猫の場合は、自宅に迎える前に獣医師に相談し寄生虫や感染病、混合ワクチンなどを徹底することが大切です。
中には、同じ環境に部屋を隔離していても飼い主を介して感染する病気もあるため、手洗いや洋服を着替えるなどの衛生管理もしっかり行いましょう。
上記の病気のほとんどがワクチンで防ぐことのできる病気でもあります。
新入り猫はもちろん、先住猫にもワクチン接種をしておきましょう。
お互いの距離が保てるスペースを確保する
猫は縄張り意識が強いため、お互いの距離が十分保てるスペースを確保しましょう。
それぞれが自由に行き来できる部屋が、猫1匹に対して1部屋あることが理想です。
SNSやテレビなどを見ていると、2匹以上の猫が仲良く寄り添っている光景を見かけます。
しかし、実は兄弟や親子ではない猫同士が同じ環境で仲良く生活することは、とても稀なこと。
万が一、先住猫と新入り猫の相性がイマイチでも、お互いがそれぞれのスペースでリラックスできる環境を確保してあげることが大切です。
個別の猫用品を用意する
水飲みやフード容器は、それぞれ別のものを用意しましょう。
水飲みやフード容器にほかの猫の匂いがついているのを嫌がる猫もいます。
最初のうちは同じ空間で食事をすることも嫌がる可能性があるので、水飲みやフード容器だけでなく部屋も別々にするのがおすすめ。
お互いが安心して水分補給や食事できる環境を整えましょう。
脱走に気を付ける
猫は環境の変化に弱い動物です。
先住猫は自分の縄張りにほかの猫がやってきて心が不安定な状態。
新入り猫がやってきたことで本来の居場所が落ち着かなくなってしまい、ふとした拍子に脱走してしまうことがあります。
新入り猫も新しい環境に加えて、ほかの猫の縄張りで生活するため落ち着かない状況です。
玄関に二重扉を設置したり、窓ストッパーを取り付けたりして対策を徹底しましょう。
脱走対策の記事はこちら!
先住猫と新入り猫を仲良くさせるためのコツ

次に、先住猫と新入り猫を仲良くさせるためのコツをご紹介します。
基本的には以下の①〜⑥までの流れに沿って慣れさせていくのが理想ですが、仲良くなるスピードや猫の性格はその子によって異なります。
①お互いを別室に隔離する
②匂いの交換
③ケージに入れて対面させる
④新入り猫のケージを先住猫と同じ空間に置く
⑤ケージから出して徐々に慣れさせる
⑥同じ空間・時間帯で食事を与える
途中で、どちらかが激しいストレスを感じているようであれば、前の段階に戻しましょう。
早く仲良くなってほしいからといって、無理やり対面させたり関係性が不十分な状態で同じ環境で生活させたりしないように注意してくださいね。
①お互いを別室に隔離する
まずは、お互いを対面させず別々の部屋に隔離しましょう。
いきなり対面させてしまうと、威嚇したり相手に攻撃したりして不仲の原因になってしまいます。
強いストレスを与えてしまうだけでなく、猫パンチなどで怪我をさせてしまうこともあるため、最初のうちはお互いの気配に慣れさせる程度にするとよいでしょう。
②匂いの交換
猫は聴覚や視覚に優れた動物です。
相手の姿は見えていなくても、ちょっとした物音や気配、匂いなどによって存在を認識しています。
対面させる前にお互いが使った布団などで匂いを交換し、合わせる前の準備を行いましょう。
最初は匂いに興味を示したり、威嚇したりする可能性がありますが、繰り返していくうちに匂いを認知し慣れていくはずですよ。
③ケージに入れて対面させる
お互いの匂いを認識し、警戒しなくなったら次にケージ越しに対面させましょう。
ケージ越しでも威嚇したりストレスを感じていたりするようであれば、無理に対面させずすぐに離してあげてください。
対面させる際は、事故防止のためにも必ず近くで飼い主さんが見守り、外出するときや飼い主さんが離れる際は別々の部屋に移動してくださいね。
④新入り猫のケージを先住猫と同じ空間に置く
何度かケージ越しでの対面を重ね、慣れてきたら新入り猫のケージを先住猫と同じ空間に置きましょう。
ともに過ごす時間を徐々に増やし、匂いを嗅ぎ合ったりケージ越しにすりよったりする行動が見られたら良好なサインです。
ただし、どちらかが威嚇したり、怯えていたりする様子があれば③に戻してケージを隔離し、数日時間を置いてから再度トライしてみてください。
⑤ケージから出して徐々に慣れさせる
ケージ越しでの対面や同じ空間での生活に慣れてきたら、いよいよ直接対面です。
最初は数分からスタートし、徐々に一緒に過ごす時間を増やします。
直接対面するときは、できるだけ飼い主さんが近くで見守り外出するときはケージに入れましょう。
関係がまだ浅い段階では一見仲良く接していても、些細なことがきっかけで喧嘩に発展し怪我をする可能性があるからです。
⑥同じ空間・時間帯で食事を与える
交流時間が増え、とくに問題なさそうであれば同じタイミングでごはんを与えてみましょう。
一緒に食事をとることで、より一層関係性を深めることができます。
最初はお互いが安心して食事できる距離に器を離し、徐々に近づけていくことで並んで食事をとることができますよ。
【実体験】新入り猫(子猫)と先住猫(1歳)が仲良くなるまで

上記では、先住猫と新入り猫が仲良くなるまでの基本的な方法について解説しました。
ここでは、我が家の先住猫と新入り猫が仲良くなるまでの実体験をご紹介します。
一歳のメス猫と生後数週間の新入り子猫。初めての対面!
我が家にはまだ一歳のメスの三毛猫がいました。
そこに当時勤めていた会社の取引先のお客さんから「子猫を保護した」と相談され、そのまま我が家の一員になることに。
最初の数日は対面させない予定でしたが、もともとほかの猫に興味津々な先住猫はすぐに子猫と仲良くなろうとしている様子でした。
子猫の方は先住猫にまるで興味なし…笑
お互いの性格が合うようで、病院で検査後は先ほどご紹介した隔離期間や匂い交換などのステップは踏みませんでした。
新入り猫と友達になりたい先住猫、体格差にヒヤヒヤ…
ケージ越しでの対面を数日行い、お互いに怯える様子や威嚇する様子が全くみられなかったため予定より早い段階で直接対面に踏み切りました。
新しい友達と早く遊びたい先住猫とよちよち歩きの子猫。
最初は先住猫の力加減が分からず、ところどころで飼い主が仲裁に入りました。
直接対面初日で、先住猫のご飯を食べようとしたり一緒に猫用ミルクを飲んだりと、仲良くなるまでのスピードはかなり早く、なかなか珍しいケースだったと思います。
子猫の成長とともにお互いの社会生が身に付く
新入り猫が来る前の先住猫は、兄弟やほかの猫との関わりがないまま幼少期を過ごしたため、飼い主に対して力加減ができませんでした。
しかし、新入り猫が来たことで「これをやったら痛い」「こうしたら相手が怒る」などの猫の社会性を身につけ、子猫の成長とともに先住猫も大人になりました。
先住猫は、自分のごはんやおやつを譲ってあげたり、一生懸命毛づくろいしたりする様子も見られ、まるで母性とも捉えられるような行動に飼い主もびっくり。
先住猫が2歳、新入り猫が1歳となった現在、一緒に鬼ごっこしたり抱き合って眠ったりするほど仲の良い家族になりました(^-^)
【実体験】2匹目を迎えてよかったこと

当時、会社員だった私は不規則な生活が続き、決して愛猫との時間が十分に取れていたわけではありません。
主人は自宅で在宅ワークですが、仕事中は構ってあげることができず1匹で過ごす時間が多いことにずっと悩んでいました。
そんな中、新入り猫との出会いをきっかけに我が家は2匹目を決意。
我が家の場合、新入り猫が来てから先住猫に対してずっと悩んでいた問題がほとんど解決しました。
先住猫の噛み癖が治った
飼い主の仕事中や食事中構って欲しさに飼い主にしつこく噛み付いたり鳴いたりすることが多くありました。
飼い主もできる限り構ってあげてはいたものの、仕事中などでどうしても手が離せないこともあります。
新入り猫が来てからは、飼い主がいない時間帯や構ってあげられないときに一緒に寝たり、遊んだりして猫同士の時間を楽しんでくれるようになりました。

飼い主
社会性が身について、噛む力を手加減できるようにもなったよ!
お留守番のときに安心
買い物に行ったり、休日にお出かけしたりして長時間家を空けることもあります。
猫は基本的に単独行動をする動物なので、お留守番が嫌いなわけではないですが、なかには飼い主さんがいないと寂しくなってしまう猫もいます。
一緒にお留守番できる相手がいることで、飼い主さんがいないときでもストレスなく過ごせるはずです。

飼い主
先住猫はお留守番のときに、後追いしなくなったよ!
運動不足の解消
猫種や年齢、体力などによって異なりますが、猫は基本的に1回10分程度の運動を1日2回以上行うのがベストと言われています。
遊び相手ができたことで、鬼ごっこしたりキャットタワーに登ったりして運動時間が増えました。
飼い主が猫じゃらしなどを使って遊ぶよりも、全身を使って運動するので太りにくくなる効果も期待できます。

みけぽん
就寝前と早朝に大運動会が始まるよ!
お互いの社会生が身に付いた
通常、猫は生後2週間から8週間ごろまでに、兄弟や母猫と一緒に社会性を身につけます。
遊びを通して噛む力加減やコミュニケーションの取り方などを学びますが、我が家の場合、先住猫と新入り猫どちらも兄弟と過ごした時間がほとんどない保護猫です。
当時、新入り猫は生後数週間の子猫でこれから社会性を身につけるのにちょうどいい時期。
一方、先住猫はすでに1歳でしたが子猫の成長とともに力加減や毛づくろいのマナーなどを学んでいきました。
多頭飼いの注意点

ここでは、多頭飼いをするときの注意点について解説します。
飼い主さんのちょっとした行動で、猫同士の関係が悪化するだけでなく、飼い主さんと猫の関係性が悪くなってしまうことも。
正しい知識を身につけて、できるだけストレスを与えないように心がけましょう。
何ごとも先住猫が優先
新入り猫を迎えたら、先住猫を優先に接してあげましょう。
先住猫はもともと家の中全てが自分の縄張り。
ある日突然新入り猫が現れて、自分の縄張りが侵略され飼い主さんまでも新入り猫注目してしまったら、とてもいい気はしません。
「今までは自分が注目されていたのに」という嫉妬心から、飼い主がいないときに意地悪をしたり、不仲の原因になったりすることもあります。
ごはんやおやつを与える順番、遊ぶ順番、撫でる順番など、全てにおいて先住猫を優先してあげましょう。
食事管理に気を付ける
多頭飼いの場合は、猫それぞれの食事管理にも注意が必要です。
猫の年齢や持病の有無などによって専用のフードを与えている場合は、同居する猫が食べないように気をつけましょう。
ほかの猫のごはんが気になって、飼い主さんが目を離した隙に相手のごはんをつまみ食いしてしまうことも。
それぞれが十分に食事や水分補給できているかどうかこまめにチェックしてあげてくださいね!
トイレは猫1匹に対して1個
基本的に猫のトイレは1匹につき1個がマストです。
1匹ずつトイレを与えることで、おしっこやうんちの回数、下痢などの健康状態をしっかり把握することができます。
また、猫は汚れたトイレを嫌うため、ほかの猫の匂いがすると我慢してしまうことも。
トイレを我慢すると膀胱炎などの病気のリスクも高まるため、しっかり管理してあげましょう。
避妊・去勢手術は早めに行う
猫の避妊・去勢は、生後約6ヶ月の初めての発情期を迎える前に行うのが理想です。
避妊・去勢を行わないと、問題行動を起こしたり、将来の病気のリスクが高まったりするためできるだけ早い段階で手術するのがおすすめです。

飼い主
避妊・去勢手術を行わず、子猫が生まれ手に負えなくなってしまう事例も。
望まない命を増やさないためにも、早めの避妊・去勢手術を行いましょう。
多頭飼いが失敗しやすい猫の特徴

猫の年齢や性別などによっては、いくら時間をかけて慣れさせようとしても多頭飼いが難しい場合があります。
最後に、多頭飼いが失敗しやすい猫の特徴をご紹介します。
オス同士の場合
成猫のオス同士の場合、縄張り意識が強いため相性が合わない可能性が高いと言えます。
とくに、去勢していない猫の場合、大きな喧嘩につながりやすく怪我をしてしまう可能性も。
喧嘩に至らなくても、お互いにとってストレスとなる可能性が高いため注意が必要です。
先住猫と新入り猫の年齢差が離れている場合
猫同士の年齢が若ければ若いほど仲良くなりやすい傾向にあります。
成猫の先住猫と子猫の場合でも関係が良好になる可能性は高いです。
しかし、先住猫がシニア猫で新入り猫が子猫または若い場合は運動量や好奇心などの違いからストレスになる可能性があるため要注意。
シニア猫の場合は、今後通院が必要だったり介護が必要になったりするため、できる限り今まで通りの生活を維持してあげることが望ましいです。

飼い主
シニア猫と若い猫は、食事内容も異なるから若い猫との同居には十分な配慮が必要だよ!
まとめ

今回は、先住猫と新入り猫が仲良くなるまでにやるべきことや注意点などについて解説しました。
先住猫の性格や性別などによって仲良くなるスピードはさまざま。
中には、どんなに時間をかけても仲良くなるのが難しい猫もいます。
2匹目を検討している方は、先住猫の性格をしっかり把握した上で迎え入れましょう。
保護猫の場合は、トライアル期間を設けて相性を見極めてあげてくださいね。
多頭飼いを成功させるためには、飼い主さんが無理に仲良くさせようとするのではなく、猫同士のペースに合わせて気長に様子を見守ってあげることが大切です。
こちらの記事もおすすめ!
– キャトヘルスアドバイザー
– 猫の健康管理インストラクター
– 保護猫歴10年
– 2匹の保護猫と暮らす
猫と飼い主さんにとって快適な暮らし、愛猫といつまでも楽しく暮らすための知識を得るサポートをします。